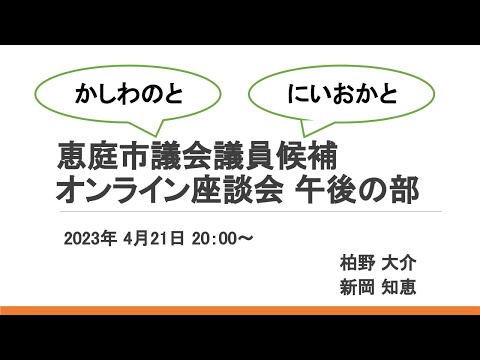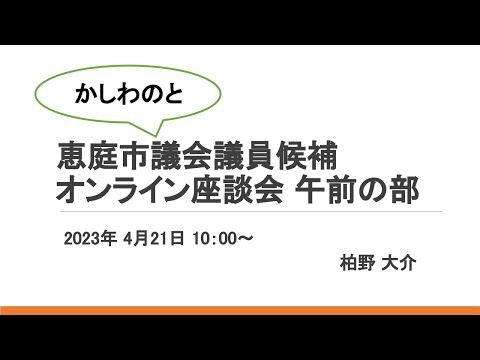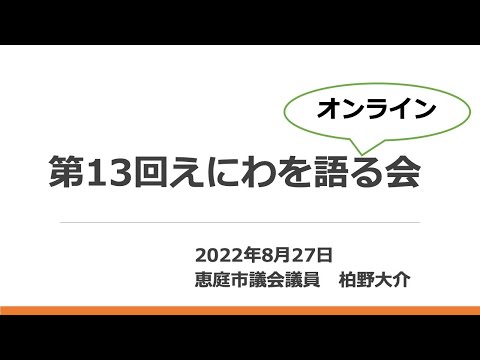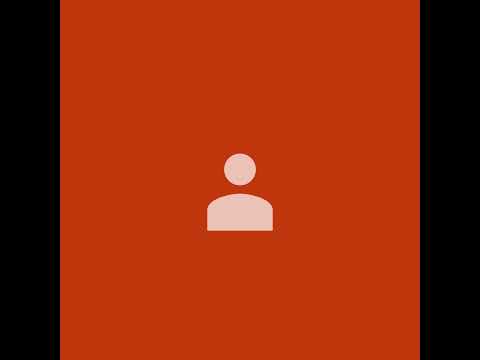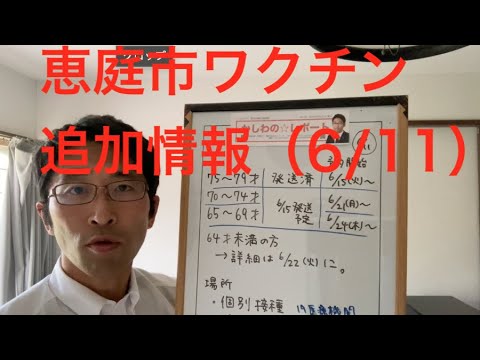北海道恵庭市議会議員
かしわの大介
一方通行の政治を変える
Pick Up
ブログ
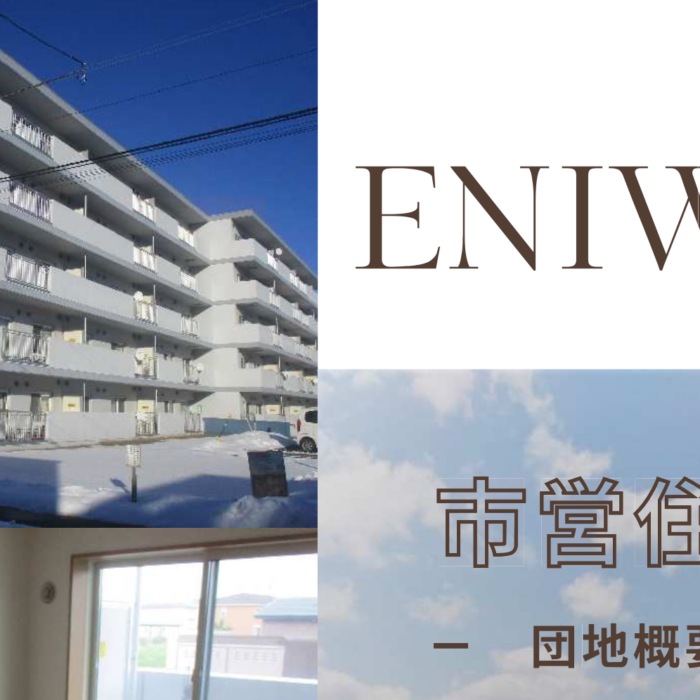
お知らせ
2026/02/22
市営住宅、指定管理者移行に関する資料
市営住宅の指定管理者制度移行に関連して、現在居住されている方に対する説明が十分に行われていないというお話を伺いました。関連する資料を掲載します。
・市営住宅指定管理者制度導入に関するサウンディング型市場調査結果について(令和7年3月14日 経済建設常任委員会 資料NO14)
8c8611fedbeb4763eb2132643172825dダウンロード
・市営住宅の指定管理者制度の導入について(令和7年6月20日 経済建設常任委員会 資料NO10)
b42faf87ed3147de1d076f1da87cc2fcダウンロード
・市営住宅の指定管理者の公募について(報告)(令和7年9月2日 経済建設常任委員会 資料NO8、別紙1、別紙2)
79616e334a7b3afc77dd4da9f7ce1530ダウンロード
10790c6247c0d32c5a7c1f5563b0acfbダウンロード
5d18aaa34bd0493453ef9519438cf33cダウンロード

お知らせ
2026/02/20
まちを思う熱意
4年前に続き、地域課題を解決する担い手として、地方議会をめざす人たちを育てる場をつくります。
https://greenseed21.jp/TrainingCourse.html
恵庭はもちろんですが、他のまちでも、地域のために働いてみたいと思う方は、私たち運営側としても高い熱量で向き合いたいと思っていますので、ぜひご参加ください。
詳しくはグリーンシード21のウェブサイトをご覧ください。
なお、4年前は約50名の受講生にご参加いただき、20名ほどが立候補をし、13名の地方議員と1名の首長を輩出することができました。
今回は実際に受講して議員になったメンバーも運営側として、より当事者のニーズに沿う内容としていく予定です。

議会報告
2026/02/19
市民スキー場子ども料金無償化は否決
本日2/19から、令和8年第1回定例会が始まりました。
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/shigikai/kaiginogoannnai/5/14168.html
9e715bf42878d28707cfe5058d41d087ダウンロード
日程はこちらの通りで、一般質問は2/25〜3/2、市民と歩む会の新岡、柏野は、3/2(月)10:00〜の予定です。
一般質問の通告内容はこちらです。
650139eb0a6dac0d527583c69c1b8ce5ダウンロード
11月に提案したスキー場の子どもリフト料金の無償化が、閉会中に審査されました。委員会では、非常に残念なことに、質疑もなく否決となり、本日の本会議採決でも、賛成4(小林議員、太田議員、新岡、柏野)で否決となりました。
26/1/26 厚生消防常任委員会
https://youtu.be/tyq46RYvULA?si=60J_a2CH-mjo13fu&t=100
私たちの力不足もあったと思いますが、冬季スポーツの振興のための提案が実らず、非常に残念です。
提案の詳細はこちらもご覧ください。
https://kashiwano.info/article-7081.html

政治と金
2026/01/20
報酬に対する考え
こちらの記事に対するコメントをいただき、お返事を書いたのですが、結構な分量になったので、記事としても掲載しておこうと思います。
2025/12/28 議員のボーナスを上げる前にhttps://kashiwano.info/article-7096.html
以下、コメントへの返信から転載
--まず、報酬の引き上げについて、私は基本的に消極的です。定数を削減することは、議員になろうとする人にとってハードルがあがるため望ましくないとこれまでは考え、そう主張してきました。報酬については、他の会派などから引き上げを求める意見、提案に対して、議会の取り組みが市民から評価され、上げるべきだという声が大きくなったときには反対はしないが、現状そういう段階ではないという考えを述べています。
なお、過去の報酬に関する記事は、カテゴリ『政治と金」で見ることができますが、主なものはこうした記事があります。(専業を求めるのであれば日給制は妥当ではないと考えています。)
2015/03/28給料いつの間にあげたの?!https://kashiwano.info/article-2197.html
2009/06/11議員報酬の削減、6月分期末手当https://kashiwano.info/article-608.html
2007/12/25報酬のあり方https://kashiwano.info/article-347.html
全国の市議会の報酬を調査したデータとしては、全国市議会議長会の調査があります。
市議会議員定数・報酬に関する調査結果:令和6年12月31日現在(全国市議会議長会)https://www.si-gichokai.jp/research/teisu/1207661_1954.html
ただ、こちらは年収ではなく、報酬月額での調査です。
北海道内においては、恵庭と同様に、報酬月額を抑えて、期末手当を高く設定している市が多いです。
一般職の職員と違い、議員は議会において議決という形で、政策の最終的な判断をしています。その結果として、税収の増減や決算指標に差がつくのであれば、そうした結果を反映させられる仕組みとするべきで、それが審議会への答申ではないかと思います。
現状では、人事院勧告に準ずる形で、ほとんどのまちが横並びで引き上げを提案し、だいたい人口規模に応じて報酬額が設定されているような状況です。
近隣市の報酬総額(年収)を比較したグラフはこちらの「審議会資料」P3にあります。
R7shiryouダウンロード
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/soumubu/shokuinka/fuzokukikanto/1/22099.html